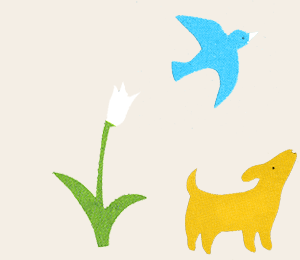- 中南米
- 国連機関等
- 政府
- 教育研究機関
- NGO/NPO
- 企業
- メディア
- その他
- 会議
【COP30について】
COP30は、11月6日~7日の首脳級会議(COP30サミット)からスタートし、政府各国の交渉と同時に、様々な展示やセミナーなどが11月10~21日の期間に開催されます。COP30議長国のブラジルは、交渉から実施へと焦点を移行させることを目的として、詳細な「テーマ別デー」のカレンダーを中心に会議を構成しています。このプログラムは、「森林、海洋、生物多様性」や「都市、インフラ、水」といったテーマを含む6つの主要な「アクション・アジェンダ」の柱に基づいています。その目的は、COPを具体的な成果とパートナーシップのためのグローバルなプラットフォームへと転換させ、第1回グローバル・ストックテイクの成果を、市民社会、産業界、学術界、地方自治体など、幅広い非国家アクターによる現実世界の解決策と結びつけることにあります。
この「テーマ別デー」は、適応分野においても重要な注目ポイントです。冒頭2日間である11月10日~11日が、「適応、都市、インフラ、水」に充てられており、これらの議題が持つ緊急性と基礎的な重要性の表れであるといえます。この期間中には、バイオエコノミーや循環経済といった関連テーマも取り上げられます。その後の日程では、保健、正義、人権(11月12日~13日)や、食料・農業(11月19日~20日)など、相互に関連する課題が扱われ、気候レジリエンスのあらゆる側面を議論するための包括的なフォーラムが形成されます。また、保健、正義、人権と共に、世界倫理全体評価(Global Ethical Stocktake)も形成されます。世界倫理全体評価はブラジル議長国と国連が主導する新たなイニシアチブであり、技術的な評価を補完し、倫理的側面を気候交渉に統合することで、次期国別削減目標(NDC)の策定に情報を提供することを目的としています。

【COPと適応の歩み】
COPとは、Conference of Parties(締約国会議)の略で、気候変動問題の文脈でCOPといえば国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の締約国会議のことを指します。1997年第3回目の会議(COP3)で採択された京都議定書では2020年までの目標が定められ、2015年第21回の会議(COP21)では、2020年以降の取り組みを決めるパリ協定が採択されました。ほぼ毎年、その実現のために、必要に応じた追加の議論や取り組みの進捗確認が行われています。
当初は締結国の国際会議でしたが、気候変動の取り組みに全てのステークホルダーを巻き込む重要性から、近年は地方自治体やNGO、民間企業などの非国家アクターの参加も促され、活発な参加が見られるようになりました。登録NGO数は2022年時点で約3,000に登ります。
適応に関しては、パリ協定7条(※1)において、「適応に関する世界全体の目標(Global Goal on Adaptation: GGA)」が、世界で目指すべき適応の目標として定められました。 2023年UAEのドバイで開催されたCOP28では、GGAの達成及び進捗評価をガイドすることを目的に、「グローバルな気候レジリエンスのためのUAEフレームワーク」が採択されました。そこでは7つのテーマ別及び4つの適応政策プロセス別の目標が設定され、2ヵ年計画でこれらの目標に付随する指標を取りまとめることが決まりました。この2ヵ年計画の終了年である今年のCOP30では、この作業の成果物である指標リストとその運用指針が取りまとめられる予定です。
※1 パリ協定7条1項
締約国は、第2条に定める気温に関する目標の文脈において、持続可能な開発に貢献し、及び適応に関する適当な対応を確保するため、この協定により、気候変動への適応に関する能力の向上並びに気候変動に対する強靱性の強化及びぜい弱性の減少という適応に関する世界全体の目標を定める
【適応分野に関連したCOP30注目ポイント】
●注目ポイント① GGAの達成度を測る指標の決定とその後
世界的な適応目標であるGGAと、それに紐づくUAEフレームワークは、国際的な適応の進捗を測る重要な枠組みです。COP30では、GGA指標の合意に向けた最終確認が焦点となり、GGAの達成に向けた進捗度を測定するための指標リストの最終合意とその運用に向けた指針の策定が主要な議題となります。前回のCOP29では、「指標に関するUAEベレン作業計画」、「GGAに関する全般的な事項」、「変革的適応」の3項目に沿った議論が行われました。UAE-ベレン作業計画の最終成果物として、100個以内の管理可能な指標セットを策定することが決定したことは大きな成果でしたが、指標の設定や報告の仕組みに関して活発に議論されるも、先進国と途上国の間で「どの指標を、どの程度統一的に適用すべきか」といった点で依然として大きな隔たりが存在していました。COP30では、この隔たりをどう埋め、GGAの進捗を可視化し評価する仕組みをつくるかが交渉の焦点となるとともに、各国での運用や変革的適応の促進がどの程度議論に反映されるかが注目されます。
UAEベレン作業計画開始当初は、気候リスク低減や強靭性向上に関するアウトプット指標と、社会経済的影響を捉えるアウトカム指標の双方を合わせ、1万個程度の指標が提案されていました。その後の交渉や専門家の作業を経て数が絞り込まれ、COP30では、気候影響の把握や適応策の効果測定に活用可能と考えられる指標を100個以内に絞り込んだ策定案について合意がなされる見通しです。分野間で優先度が異なり合意に至らなかった項目や、特に資金に関連する指標について、さらに時間をかけて調整されていく見込みです。
合意された指標は、国家や地域レベルにおける適応策を検討する材料となり、企業や自治体が実施するプロジェクト等の効果の評価にも直結します。また、開発途上国における実現可能性の観点から、資金や技術的支援が十分でない国での指標適用の課題も重要な議論のポイントとして注視すべきところです。また、レビューの頻度や手法といった実務的な運用方法についても、審議が行われることになると考えられます。適応分野において国際的な合意枠組みがつくられますが、一方で、その実効性には不確実性も残り、各国がどの程度実際の政策・施策に落とし込めるかまでは未定であるといえます。実務的観点からは、各国の能力差やデータ不足を踏まえたソフトランディング型の合意が見込まれる一方、国際社会が適応の測定と評価に向けて歩みを進める一つのマイルストーンとなることが期待されます。
「バクー適応ロードマップ(BAR)」は、COP29で採択された、GGAに関する取組促進を目的としたロードマップであり、GGAに関して、指標策定後のより長期的かつ広範な取組が示される見込みです。2025年6月の補助機関会合(SB)では、BARの様式について議論が行われましたが、GGAの指標と各国の適応計画の整合についてどこまで制度化・標準化すべきか、国際協力・包摂性・資金提供などの実施手段に関する優先順位と制度設計への具体性をどの程度規定するか等が争点となり、意見の一致がみられませんでした。COP30では、これらの争点もふまえ、BARにおいて、GGAに関連する今後の広範な議論や活動の指針が示されることが期待されます。
GGAやBARは国家レベル中心の枠組みですが、COP30では地域や現場での実装も重視される見込みです。地域レベルでの適応策では、先住民の伝統的知識、地域住民の参加や知見を政策に反映させる仕組みや、気候影響や社会状況に応じた柔軟な適応策の設計が不可欠です。また、民間企業による地域プロジェクトへの投資や技術提供も、地域実装の成功に大きく寄与する要素です。地域に根ざした実装の視点を持つことが、効果的な適応策の評価や実践に直接関連する点も多くみられるのではないでしょうか。国家レベルの指標・目標を地域やコミュニティの現場に落とし込む視点も含め、「グローバル→ナショナル→ローカル」のつながりの強化も期待されている点です。
総じて、COP30では指標の暫定的採択(段階的合意)とBARによる実施ロードマップの方向付けが現実的な成果ラインであり、これがGGAを制度的に動かす第一歩となる可能性が高いと考えられます。ただし最終的な指標数やBARの詳細運用は交渉の妥結次第で変動する点には留意する必要があります。
●注目ポイント② 変革的適応の推進
気候変動影響が世界中で顕著になる中、「変革的適応(transformational adaptation)」に対する注目がこれまで以上に高まっています。COP28のグローバル・ストックテイク(GST)決定およびGGA決定では、長期的な変革的適応と漸進的適応を含む適応努力の重要性が認識され、COP29以降、UNFCCC事務局が取りまとめた変革的適応の定義や進捗状況の評価手法等に関する報告書(要約版)を参照して議論が行われてきました。一般的に、漸進的適応は「一定規模でシステム又はプロセスの本質と一貫性を維持することを狙いの中心とする適応行動」、変革的適応は「気候とその影響に応じて、あるシステムの基本的性質を変える適応」と定義されています1。一言で表現するならば、漸進的適応は「システムの調整(既存システムを前提に調整・強化するアプローチ)」、変革的適応は「システムの転換(システムの基本構造を見直し、構造転換するアプローチ)」です。
COP29までは「変革的適応」が注目されていましたが、国連気候変動枠組条約第62回補助機関会合(SB62)では、変革適応を含む「多様な適応アプローチ」全体に焦点を広げるべきとの意見が強まりました。これを受けてCOP30では、漸進的適応と変革的適応それぞれの役割や効果に関し、各国・各地域の異なる状況やニーズを考慮しつつ、どのようなアプローチを組み合わせることが効果的かについて議論が行われる可能性があります。また、適応アプローチの多様性を反映できる指標や、実施手段の確保、さらには各国の適応策への反映方法など、具体的な制度設計や実施支援策をめぐって交渉が進展することも期待されます。
●注目ポイント③ NAP交渉と更新された技術ガイドラインの運用開始
UNFCCC における 国別適応計画(NAP:National Adaptation Plan)プロセスは、2010年のCOP16におけるカンクン合意での決定に端を発し、主に開発途上国が中長期の適応ニーズを明確化し、適応戦略を策定・実施する枠組みとして制度化されてきました。その後、COP17 において「NAP 作成・実施の初期ガイドライン」が決定され、後発開発途上国専門家グループ(LEG)が技術ガイドラインの整備を主導しました。
現在、UNFCCCはNAPプロセス全体に関する進捗をモニタリングし、交渉の中でもNAP を定期的に議題化しています。しかし、2024年にNAPプロセス全体のアセスメントが開始されて以降、NAPプロセスに対する更なる資金・技術の支援強化を強く主張する途上国と、それに対し慎重な先進国との間で意見が対立し、実質的な合意が得られていません。
こうした中、2025年8月にNAP技術ガイドラインが約10年ぶりに更新されました。今回の改訂は、各国がNAPプロセスを進める上での実務的な参考となるもので、交渉の停滞を打開する直接的なものではないにせよ、今後のプロセス支援に資する重要なツールです。新しいガイドラインの主な特徴は以下の通りです。
A)NAPプロセスのモジュール化:
「リスク・脆弱性評価」「計画策定」「実施」「モニタリング・評価・学習(MEL)」など、NAPプロセスを複数のモジュールに整理。国ごとに進展段階に応じて柔軟に参照できるようになりました。
B)GGAとの整合性:
GGAおよびUAEフレームワークで規定された11のターゲットに対応した解説を加え、各国のNAPが国際的な目標設定や進捗評価とつながりやすくなるよう配慮されています。
C)資金・技術支援とのリンク:
NAP の計画段階から資金調達・技術協力を念頭に置き、実効性ある実施につなげる設計が強調されています。
D)評価と学習の強化:
適応行動の成果を測定・検証するためのモニタリング・評価の方法が拡充され、学習と改善の循環を重視する内容となっています。
COP30におけるNAP議題は、引き続き 「NAPプロセスのアセスメントをいかに前進させるか」の議論が中心であり、この課題を克服できなければ交渉の停滞が続く可能性があります。その一方で、更新された技術ガイドラインは、各国が最新の国際情勢を踏まえた上でNAPプロセスを進展させていく上での重要な参考資料として機能することが期待されます。
【NDC3.0と適応】
COP30は、各国が2023年の第1回グローバル・ストックテイク(GST1)の結果を踏まえ、これまで以上に高い野心と信頼性を備えた気候変動対策を表明する場として注目を集めています。NDC3.0(第3次・自国が決定する貢献:Nationally Determined Contribution)は緩和だけでなく、適応分野においても野心向上や進捗評価の枠組みを本格的に実装することが求められ、先進国・途上国を問わず、水、食料、健康、生態系、インフラ、生計、文化遺産など幅広い分野で測定可能な目標や指標の明示が奨励されています。COP30に向け各国は、GST1で顕在化した適応ギャップや資金・支援不足を受け、より明確な適応ニーズや実施計画をNDCに反映することが期待されています。
こうした流れにより、NDC3.0は単に意向を表明する政策文書の枠を超え、適応行動のモニタリングや検証、目標達成度の管理を含む包括的な国際報告ツールへ発展していくと言えます。GGA指標リストの整備が進む中、各国はNDC3.0で最新の科学や優良事例を取り入れ、透明性と比較可能性をより高めた記述が求められています。また、途上国ではこうした指標や報告を活用し、適応資金・技術支援へのアクセス改善や、定量的な支援要請の可視化にも努めはじめています。先進国には新たな資金目標への積極的貢献が期待されており、適応と緩和双方のグローバルな進捗管理が一体的に問われています。
そのような中、今後重要になってくるのが、NDCとNAPのアライメントです。NDCは、各国が国際社会に向けた約束として適応目標や支援ニーズを示す場であるのに対し、NAPは国内での実装の道筋として、気候リスク評価や適応の優先策を具体化するプロセスです。両者を結びつけることで、目標と実行が連動し、国際的な支援要請の根拠も明確になります。さらに、隔年透明性報告書(BTR)や適応コミュニケーション(AdCom)もNDCと連動させ、政策の一貫性や効果検証、透明性の強化につなげることが重要であると言えます。
このように、COP30はNDC3.0という国際ベンチマークを起点に、各国の適応目標と国内実行体制の連動性、多国間での協調強化、現場ニーズの実効的な国際化といった新たな潮流を生み出そうとしています。今後提出されるNDC3.0とその実装体制が、2026年以降のGSTや適応交渉の土台となり、「目標から実行へ」の流れと国際連携の深化がますます重視されていくでしょう。
【今年は「ネイチャーCOP」】
COP30は、史上初めてアマゾン地域・ブラジルで開催されることもあり、「ネイチャーCOP」と呼ばれています。最大の理由は、地球規模で課題となっている森林破壊・生物多様性損失と気候変動への統合的対応を、会議の中心に据える議長国ブラジルの姿勢が鮮明だからです。ブラジルは、世界最大の熱帯雨林を抱えていることもあり、アマゾン保全そのものが気候変動への鍵とされ、多くのプログラムや政策が“Nature”分野を軸に設計・提案されています。
今回特に注目されるのが「Tropical Forests Forever Facility(TFFF)」の具体化です。TFFFは、COP28でブラジルが提唱した革新的枠組みで、熱帯林国が安定的・長期的に森林保全資金を得られる仕組みを構築します。単なる炭素吸収源としてだけでなく、生態系サービス・地域社会のレジリエンス強化・生物多様性保全など、多面的な恩恵を実現するプラットフォームとして期待が集まっています。
「ネイチャーCOP」と呼ばれる背景には、これまでのCOPが温室効果ガス削減すなわち緩和中心であったのに対し、COP30では自然資本、自然を活用した解決策(NbS)、生態系回復、先住民と地域共同体の知見活用、社会的包摂、ジェンダーも含めた幅広いステークホルダーとの協調といった、「自然との共存」の観点が重視されている点が挙げられます。生物多様性条約COPと連携した、「ネイチャー・ポジティブ」な未来への明確な道筋についても注目されています。
さらにCOP30議長国が設定したAction Agendaでは、グローバル・ストックテイク(GST)や新規合同数値目標(NCQG)におけるNature分野への投資配分、現場発の優良事例紹介、包摂的イニシアティブなどが特集され、アマゾン保全・森林再生・都市-農村-沿岸の生態系連携などについても議論されています。COP30は、自然分野の歴史的な転換点として「ネイチャーCOP」と呼ばれるにふさわしい会議となることが期待されています。
【損失と損害:基金と制度レビューの焦点】
「損失と損害」に対応するための基金(FRLD)は、2023年COP28の決定に基づき運用を開始し、途上国の経済的・非経済的被害への対応を支援することを目的としています。2025年4月時点で27カ国から約7.7億米ドルの拠出が表明され、理事会は「バルバドス実施モダリティ」に基づくスタートアップ段階を承認しました。ここでは、資金基準や初期プロジェクトの仕組みが整備され、2026年末までに2.5億米ドルのグラント(無償資金)が動員される計画です。
しかし、この拠出規模は必要とされる資金のごく一部に過ぎません。推計では途上国が直面する年間ニーズは2030年までに2,900億〜5,800億米ドルに達すると予測されており、これは表明額の0.2%にも満たない水準です。この深刻な乖離は、COP30でFRLDがどのように機能拡大を図り、資金アクセスのモダリティや「特に脆弱な国」の優先基準を整備するかが最大の論点になる理由といえます。
一方で、2013年に設立されたワルシャワ国際メカニズム(WIM)は、知識の向上・連携強化・行動と支援の促進という3つの機能を通じて損失と損害に取り組んできました。技術支援のためのサンティアゴ・ネットワークの始動など一定の前進はあるものの、義務付けられた5年レビューはCOP29で最終化せず、2025年6月の補助機関会合でも合意に達せずに持ち越されました。
争点の核心は、WIMの範囲に資金メカニズムをどこまで含めるかという点です。途上国は資金スケールアップをWIMの中心機能と位置付け、明確な位置づけをレビューに反映させるよう主張していますが、一部先進国は資金交渉を切り離すべきだと反発しています。この対立はCOP30に引き継がれ、ベレンでの交渉の中心的課題になる見込みです。
こうした議論は、新設されたFRLD、WIM、サンティアゴ・ネットワークの三者がいかに相互補完的に機能するかを方向づけるものです。COP30での決定は、制度間の一貫性を確保しつつ、脆弱国に対して知識・技術・資金をバランスよく提供できる包括的な仕組みを築く上で極めて重要です。今後の交渉は、損失と損害をめぐる国際制度を実効的に整える転換点となることが期待されています。
【NGO・民間企業・自治体の取組とCOP30における位置付け】
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の交渉過程では、各国政府が主要なアクターである一方、NGO、民間企業、自治体など非国家主体(non-Party stakeholders)の役割が年々増大しています。COP30でも、こうした主体の行動が交渉成果を補完し、実践的な適応・緩和の加速に寄与する点が大きな焦点となります。
民間企業は、気候リスクが事業活動や投資に直結することから、適応・緩和の両面で積極的な動きが広がっています。再保険会社による気候リスク評価サービス、農業関連企業の気候適応型品種開発、IT企業による気象データ活用の高度化など、革新的な技術や市場メカニズムを通じた実践と貢献が期待されています。さらに、ESG(Environment, Social, Governance)投資やTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)など、企業報告制度と結び付いた気候対応が国際的に進展しており、COP30では民間資金を適応投資へどう誘導するかが大きな論点となりそうです。
自治体もまた、気候変動の最前線で行動する主体としての存在感が高まっています。都市ごとの適応計画やグリーンインフラ整備、早期警戒システムの導入などが共有されていますし、地方レベルの実践は、国家のNAP(国別適応計画)の実装を支えると同時に、地域特有の課題を踏まえた柔軟なアプローチを可能にしています。
そしてNGOは、市民社会の立場から、脆弱なコミュニティや先住民の声を国際交渉に反映させる重要な役割を担っています。特に、公平な資金配分やジェンダー平等の観点からのモニタリング、ガバナンス改善を求める活動は、政府交渉団に対しても機能しています。また、現場での小規模プロジェクトの成果を共有し、スケールアップや政策転換につなげる媒介役としても注目されています。
こうした非国家主体の取組みは、UNFCCC事務局が推進する「グローバル・クライメート・アクション・ポータル」などを通じて可視化され、広く発信されています。COP30では、各国政府による政策枠組みと、企業・自治体・NGOによる実践的な行動とをどう結び付け、全体の野心向上に資するかが重要な論点となると考えられます。結論として、政府交渉の成果のみならず、多様な主体の取り組みを含めた「全社会的な気候行動(whole-of-society approach)」がCOP30の成功の鍵となります。
【COP30のスケジュール】
COP30は、11月6日~7日の首脳級会議(COP30サミット)からスタートし、政府各国の交渉と同時に、様々な展示やセミナーなどが11月10~21日の期間に開催されます。COP30議長国のブラジルは、交渉から実施へと焦点を移行させることを目的として、詳細な「テーマ別デー」のカレンダーを中心に会議を構成しています。このプログラムは、「森林、海洋、生物多様性」や「都市、インフラ、水」といったテーマを含む6つの主要な「アクション・アジェンダ」の柱に基づいています。その目的は、COPを具体的な成果とパートナーシップのためのグローバルなプラットフォームへと転換させ、第1回グローバル・ストックテイクの成果を、市民社会、産業界、学術界、地方自治体など、幅広い非国家アクターによる現実世界の解決策と結びつけることにあります。
この「テーマ別デー」は、適応分野においても重要な注目ポイントです。冒頭2日間である11月10日~11日が、「適応、都市、インフラ、水」に充てられており、これらの議題が持つ緊急性と基礎的な重要性の表れであるといえます。この期間中には、バイオエコノミーや循環経済といった関連テーマも取り上げられます。その後の日程では、保健、正義、人権(11月12日~13日)や、食料・農業(11月19日~20日)など、相互に関連する課題が扱われ、気候レジリエンスのあらゆる側面を議論するための包括的なフォーラムが形成されます。また、保健、正義、人権と共に、世界倫理全体評価(Global Ethical Stocktake)も形成されます。世界倫理全体評価はブラジル議長国と国連が主導する新たなイニシアチブであり、技術的な評価を補完し、倫理的側面を気候交渉に統合することで、次期国別削減目標(NDC)の策定に情報を提供することを目的としています。
【テーマ別デーのトピック】
11.10(月)―11.11(火)
適応、都市、インフラ、水、廃棄物、地方自治体、バイオエコノミー、循環経済、科学、技術、人工知能
11.12(水)―11.13(木)
健康、雇用、教育、文化、正義と人権、情報、世界倫理全体評価(Global Ethical Stocktake)、労働者
11.14(金)―11.15(土)
エネルギー、産業、交通、貿易、金融、炭素市場、二酸化炭素以外の温室効果ガス
11.17(月)―11.18(火)
森林、海洋、生物多様性、中小企業(SME)、先住民、地域・伝統コミュニティ、子どもと若者
11.19(水)―11.20(木)
農業、食料システムと食料安全保障、漁業、家族農業、女性とジェンダー
【COP30公式サイト】
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/cop/index.html
【COP30変遷とポイント】
https://cop30.br/en/news-about-cop30/cop30-announces-ambitious-thematic-days-invites-the-world-to-belem